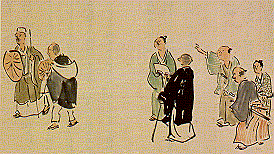
芭蕉db
(千住旅立ち:元禄2年3月27日)
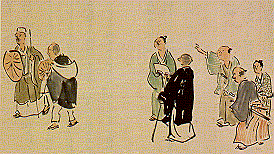
彌生も末の七日*、明ぼのゝ空朧々として、月は在明にて光おさまれる物から*、不二の峰幽かに みえて、上野・谷中の花の梢*、又いつかは*と心ぼそし。むつましきかぎり*は宵よりつどひて、舟に乗て送る*。千じゆ*と云所にて 船をあがれば、前途三千里*のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそゝぐ。
(ゆくはるや とりなきうおの めはなみだ)

(ゆくはるや とりなきうおの めはなみだ)
なお、 この句そのものは、この折につくられたものではなくて本文執筆時に改めてここに入れるために考案されたものであり、芭蕉の初案は「鮎の子の白魚送る別れかな」であったと言われている。しかし、推敲の過程でこの句に代えられた。上述のような「行く春」と「行く秋」の対象性 などの着想ができたためであろうと思われる。奥の細道は、このように多様な対称性など構造的なつくりを駆使して創作されているのである。
「行く春や鳥啼き魚の目は泪」の句碑(写真提供:牛久市森田武さん)
上野・谷中の花の梢:上野も谷中も桜の名所。ただし、すでに桜は散って芭蕉の視界に桜の花は無い。惜別の念を表現するために書かれたもの。
舟に乗て送る:深川にて乗船。この当時の風習では、長旅に出る人の送別は、一駅先の宿駅まで同行すること、また、別れるときには後ろ姿が見えなくなるまで見送ること、その際送られるものは後ろを振り返ってはいけないとされた。
千じゆ:東京都足立区 または荒川区、千住大橋付近。芭蕉がこの墨田川の右岸に上陸したか左岸であったかは不明。千住は当時、奥州街道(1597年)・日光街道(1625年)第一の宿場。ここまで芭蕉庵から約10kmある。千住に着いたのは、『曾良旅日記』によれば、「巳の下尅」というから午前11時ごろということになる。ただし、ここには曾良は不在だったはずだという説もあるので信じ難いのである。
これを矢立の初として:<これをやだてのはじめとして>。この句を旅立ちの記念として、の意。矢立は携帯用の筆記用具。筆や墨を一組として収めたもの。ここでは、「俳諧創造の旅」の象徴として込めている。
全文翻訳
今日、陰暦三月二十七日。あけぼのの空は春霞にかすみ、有明の月はすでに光を失って、富士の峰がうっすらと見えてきた。上野や谷中の桜の花には、また再び相まみえることができるのだろうかと、ふと不安が心をよぎる。親しい人々はみな前夜からやってきて、共に舟に乗って見送ってくれる。千住というところで舟をあがると、前途三千里の遥かな旅路が胸に迫って、夢まぼろしの世とはいいながら、別離の悲しみに、涙が止まらない。
行春や鳥啼魚の目は泪
この句を、この旅の最初の吟とはしたものの、後ろ髪を引かれて足が前に進まない。見送りの人々は道の真ん中に立って、後ろ姿がみえなくなるまで、見送ってくれた。