-
芭蕉db
-
奥の細道
-
(曾良との別れ 元禄2年8月5日・6日)
-
曾良は腹を病て、伊勢の国長島と云所にゆかりあれば*、先立て行に
、
-
-
行行てたふれ伏とも萩の原 曾良*
-
(ゆきゆきて たおれふすとも はぎのはら)
-
-
と書置たり。行ものゝ悲しみ、残るものゝうらみ、隻鳧*のわかれて雲にまよふがごとし。予も又
、
-
-
-
(きょうよりや かきつけけさん かさのつゆ)
-
-
大聖持*の城外、全昌寺*といふ寺にとまる。猶加賀の地也。曾良も前の夜、此寺に泊て
、
-
-
終宵秋風聞やうらの山*
-
(よもすがら あきかぜきくや うらのやま)
-
-
と残す。一夜の隔千里に同じ*。吾も秋風を聞て衆寮*に臥ば、明ぼのゝ空近う読経声すむまゝに、鐘板*鳴て食堂に入。けふは越前の国へと、心早卒にして*堂下に下るを、若き僧ども紙・硯をかゝえ、階のもとまで追来る。折節庭中の柳散れば
*、
-
-
-
(にわはきて いでばやてらに ちるやなぎ)
-
-
とりあへぬさまして、草鞋ながら書捨つ*。
-
 前へ
前へ  次へ
次へ
-
 表紙
表紙  年表
年表
-

-
今日よりや書付消さん笠の露
-
『笈の小文』でも杜国との旅で「乾坤無住同行二人」と笠の内側に書いていた。曾良との今回の旅でも同じように書付があったのであろう。しかし、胃痛に堪えず曾良は長島に旅立ち、ひとりになった今となってはこの書付は消さなくてはならない。笠についている
秋の朝露か涙の滴でこれを消そうか。
-

山中温泉の大木戸門跡にある「今日よりや書付消さん笠の露」の句碑(写真提供:牛久市森田武さん)
-

-
「行き行きてたふれ伏とも萩の原」(曾良)の句碑
三重県桑名郡長島大智院の句碑(同上)
-
庭掃いて出でばや寺に散る柳
-
旅人が寺に止めてもらった翌日は山内の清掃をして出て行くのがならわし。
なお、『芭蕉翁略伝』では、
-
同行なりける曾良、道より心地煩しくなりて、
-
我より先に伊勢の国へ行くとて、「跡あらん倒
-
れ伏すとも花野原」というふを書き置き侍るを
-
見て、いと心細かりければ
-
さびしげに書付消さん笠の露
-
とある。曾良の句も芭蕉の句も初案に近いものであろう。
-

全昌寺境内にある「庭掃いて・・」の句碑(同上)
-

「全昌寺」について
- 今回の、奥の細道を訪ねる旅で、一番親切にして頂いたのは全昌寺さんでした。北陸の空は時折小雨が降っていたが、全昌寺についた時は、本降りに成ってしまった。親切な和尚さん御夫妻に寺に上げて貰い、芭蕉談義をした。五百羅漢が有名であり、羅漢堂前の柳は、芭蕉さんが見た柳からは3代目であり、大分若木であった。曾良と一日違えで芭蕉さんが泊まった部屋は、当時の姿そのままに、近年改築されて、木の香も新しい部屋になっていた。(文と写真提供:牛久市森田武さん)
-

- 杉風が作成して、寺に寄進した「芭蕉像」は、ガラスのケースに収められて居たが、ガラス越では写真に写らないので、特別にカギを開け、写真を撮らして下さった。汐越の松の有りかを寺の奥さんに尋ねたら、「話には聞いているが、見たことは無い。確か、ゴルフ場に成ってしまったよ」と言っていた。(文と写真提供:牛久市森田武さん)
曾良は腹を病みて:曾良は、越中から金沢に入る時分から健康を害していたらしく、一笑の追善供養の句会にも遅れて参加している。但し、『曾良旅日記』では、体調については触れていないので、ここは文学的粉飾であろう。なお、曾良はその昔長島藩に仕えたことがあり、そこの大智院の住職が伯父にあたる。
「行き行きてたふれ伏とも萩の原」:『猿蓑巻の三』では、
「元禄二年翁に供(具)せられて、みちのく
より三越路にかゝり行脚しけるに、
かゞの國にていたはり侍りて、いせ
まで先達けるとて 『いづくにかたふれ臥とも萩の原』」となっている。なお、この句は、西行の歌「いづくにかねぶりねぶりて倒れ伏さむと思ふ悲しき道芝の露」(山家集)の本歌取になっている。
大聖
持:<だいしょうじ>と読む。加賀市大聖寺町。
加賀藩前田家の7万石の支城だが、徳川幕府ににらまれることを嫌って、金沢とは一体的に経営しなかったという。
全昌寺:<ぜんしょうじ>、石川県加賀市大聖寺町の曹洞宗寺院。先の山中温泉の和泉屋の菩提寺でもあり、ここの住職月印和尚は久米之助の
伯父だった。
隻鳧:<せきふ>と読む。蘇武と李陵とが匈奴に捕らえられていたのに、蘇武だけが漢に召喚されることになり、「雙鳧ともに北に飛び、一鳧ひとり南に翔ける」と李陵が別れを哀しんで詠んだ故事による。
終宵秋風聞やうらの山:<よもすがらあきかぜきくやうらのやま>。一人で泊まった寺の裏山の秋風はさみしく、心の中までしみとおってくるようだ
。
一夜の隔千里に同じ:<いちやのへだてせんりにおなじ>と読む。
蘇東坡の詩「咫尺<しせき>相見ざれば、実に千里に同じ」による。「咫」は周尺の八寸、「尺」は一尺で、転じて、極めて近い距離のこと。
衆寮:禅宗の寺の修行僧たちの寮。
鐘板:寺院で食事の合図に使う青銅製の鐘。雲板とも。
心早卒にして:<こころそうそつにして>と読む。心せく気持ち
。
折節庭中の柳散れば:<おりふしていちゅうのやなぎちれば>と読む。丁度そのとき、寺の庭の柳の木の葉が落ちたので。
とりあへぬさまして、草鞋ながら書捨つ:即興的に、草鞋を履いたまま一句を書いた、の意。
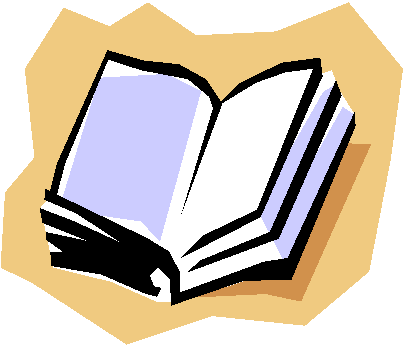
全文翻訳
曾良は、腹の具合が悪く、伊勢の国長島に親族がいるので、先に発つことにした。
行行てたふれ伏とも萩の原 曾良
と書き残して去って行った。行く者の悲しみ、残る者の無念、まさに李陵と蘇武の二人の別れにも似て、隻鳧が別れて雲に迷うとはこのことだ。私もまた一句、
今日よりや書付消さん笠の露
大聖寺の郊外に全昌寺という寺があり、ここに宿泊する。まだ、ここは加賀の国内である。曾良も前夜はここに泊まっており、
終宵秋風聞やうらの山
と一句残していた。まことに蘇東坡の詩「咫尺相見ざれば、実に千里に同じ」にあるように、一夜の隔たりは千里の距離だ。私も秋風を聞きながら、寺の宿寮に泊まる。
夜明けちかく澄んだ読経の声を聞く。やがて鐘板が鳴ったので食堂に入る。
今日は越前の国へ行くのだとあわただしく食堂を出ると、若い僧たちが紙や硯をもって、階段の下まで追ってきた。丁度そのとき庭の柳の葉の落ちるのが見えたので、
庭掃て出ばや寺に散柳
とっさの即興吟として、草鞋を履いたまま走り書きした。





