|
ふじざくら No.17
山梨県立女子短期大学図書館(2000.4) |
|
ふじざくら No.17
山梨県立女子短期大学図書館(2000.4) |
| わたしは、いろいろなことを知り、いろいろなものを読むことが好きである。それは未知のことについての興味であり、そして自分が生きている時代を知り、自分が生きていることの意味を確かめるためである。 現在ではそのための手段は多い。事実関係を知るということでは、テレビが大きい意味をもつと言えそうである。テレビは映像で示すという意味では説得力や迫力があることは確かである。テレビのプラス面は、衝撃的な出来事が目の前に現われたときには顕著である。数年前のオウム事件がそれであった。ワイドショウで取り上げられたこの宗教団体の毎日の行動があまりにもわたしの理解を越えていたために、自分が生きている時代をとらえ損なっているのではないかという思いにかられて、しばらくワイドショウ漬けになったしまった。しかしテレビのニュースは瞬時の通過的な形であり、内容は断片的である。またワイドショウは事件や芸能ゴッシプのくり返しに過ぎない(オウム後のワイド番組の印象である)。テレビはいろいろな出来事を落ち着いて確認しながら受けとめるという点では劣る。 テレビに対して印刷されたものは、自分の時間配分でていねいに読めるというメリットをもつ。色々な印刷物のなかで、読むものの筆頭は新聞である。新聞は日々の出来事(内外の政治・経済・社会・文化など)を伝える。いいかえれば、わたしたちが生きている時代を明らかにする素材を含んでいるということである。もちろん内容や書き方には新聞社の主張や、書く人の主観がまじっているから、そのまますべて「真実」であるというわけではないが、事実関係を知るスタート地点であることは確かである。 ただ新聞もまた日々の出来事に追われるという面があり、また読者の目や、時には政権の座にある人々の声を考慮して書かれる。たとえば皇室の問題である。イギリスなど他国の皇室についてはかなりの報道がなされるのに、日本の皇室については、その「尊厳」を損なうとされることについては、写真一枚に至るまで厳しい規制がある。 現在を知る上でテレビや新聞では充足されない部分が残されることになる。それを埋め合わせるものはいくつかある。たとえば、いろいろな人の話を聞くことや、色々な文献を読むことである。現在問題になっていること(たとえば家族関係の現状、子供が置かれている状況、日の丸・君が代問題など)については、論壇誌(『世界』『中央公論』など)を読み、それに関する新しい単行本を読むことになる。それによってわたしたちが生きている時代がどのような問題を抱えているかを多面的に、ある程度の深さをもって知ることができる(さらに言えば、大学で学ぶことは時代を作る人・物・心に関わる出来事の背景や相互関連を追求する知識・技術を獲得することである)。 というわけで「知ること」について、テレビは時代の雰囲気(やや怪しげなものを含む)を与える。そして新聞では日々の事実関係を確認し、雑誌や本は、時代の論点とその背後にあるものをまとめてくれる。といっても日々のせわしさの中で、割ける時間は限られている。心がけの問題として、時代を捉えつつ生きていたいということである。すべては、時代を知る・現在を知る・自分を知るということに関わることである。 |
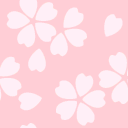
| 日本最大の蔵書量を誇り、毎日2,000人もの人が利用している国立国会図書館に、行ったことのある人は、意外にも少ないようです。そこで、国の唯一の国立の図書館としていろいろな顔を持つ「国立国会図書館」について紹介します。どんなところか一度自分の目で確かめてみませんか? |
| <特色> 国立国会図書館は、新しく出版された図書・雑誌などを国の文化財として後世に遺す使命を負っています。現在、約700万冊の図書の他、新聞、雑誌、地図、楽譜、マイクロ資料、レコード・CDなどを所蔵しており日本最大の図書館です。通常私たちが利用する開架式の図書館とは違い、参考図書など一部の資料を除いては書庫内に収納されていて、利用者の請求に応じて出納する閉架式図書館です。 |
書名 |
出版社 |
請求記号 |
| 「国立国会図書館百科」 | 出版ニュース社 | 016-Kok |
| 「図書館ハンドブック」 | 日本図書館協会 | 010-Nip |
| 「全国図書館案内上・下」 | 三一書房 | 011-Zen-1・2 |
| 「人物記念館事典」 | 日外アソシエーツ | 069-Nic |
| 4月、1年生はこれから始まろうとする学生生活に胸おどらせ、2年生は最後の学生生活を意義あるものにしようと、“新たな決意”を胸に秘める月ではないでしょうか。 そこで、皆さんが楽しく充実した学生生活を送るために3つの分野にわけて1階ロビーにて資料展示を行っています。 この紙面ではそれらの一部を紹介します。 |
『大学に行くということ、働くということ』
樋口美雄 著 岩波書店| 大学では一体何を学ぶのか、社会に出て働くとはどういうことなのか。メジャーリーグと日本のプロ野球の比較などユニークな事例で、日本社会における働くこと」と「学ぶこと」の新しい方向性が説明してあります。 |
| 大学で賢くなる人、愚かになる人、その差はどこにあるのか・・。キャンパス生活がガラリと変わる「学問と人生」の案内書です。 |
| 図書館や情報システムに存在する情報をうまく活用して、レポートや卒業論文の執筆に役立てること、及び情報探索に関する技術のマスターを目的として、教官と図書館司書が一体となって行った京都大学の授業の講義録です。 |
| 大学生活でコンピュータを役立たせるためのリテラシーを解説しています。表現力、コミュニケーション力、資料収集力、データ分析を見につけるための知識と技術を中心に説明があります。 |
| 大学で一生懸命勉強して、良い成績をとっても就職には関係ないのはなぜだろうか? 就職活動で苦労しているのは自分だけ?などの疑問とその背後にある社会的要因を解きあかそうとする内容の図書です。 |
| どの会社でも、履歴書・面接では自己PRと志望動機についての応答を最重視します。業界別に話し方、気をつけたいツボを成功例・失敗例を使って解説されており就職戦線に勝つためのポイントが示してあります。 |
| ある作品に心から陶酔することは、文学にしろ舞台や映画にしろ、なかなか得がたいものである。いわゆる「ハマ」る、ということはままある。しかし、たんなる興奮じみた高揚感ではなく、しみじみと心の深淵に達するような陶酔感となると、人生でどれほど巡り逢えるかわからない。ところで、私は舞台や映画に感銘を受けると、すぐにその原作を読みたくなる。表現方法のまったく違う両者をことさら関係づけることには異論がある人もいようが、舞台や映画の感動を別な形で再生産させ、より深い喜びを味わいたいという欲求は、しごく自然なものだと思う。その逆の場合もある。小説や戯曲を読みながら、自分だけの「舞台」や「映画」を創り上げてしまうのである。このように、文学と舞台・映画という異なる表現世界を往来するうちに、えもいわれぬ陶酔に陥ることがある。 去年、プッチーニ作曲の『マノン・レスコー』というオペラを観た。かつて原作であるアヴェ・プレヴォーの小説を読んだとき、マノンとデ・グリューの哀しい恋物語が慟哭に似た悲痛な想いを呼び起こして、なかなか私の心から去らなかった。それがオペラではどうなるのか―プッチーニのオペラは「甘美」そのものだった。世の中にこれほど甘美な音楽、そして歌詞があろうか、と思われるほどに。デ・グリューがマノンに名前を問う出会いの場面で、私は恋愛の真髄をみた気がした。小説で別れの慟哭を、そしてオペラで出会いの甘美を知った。どちらも深淵において恋愛の本質を語ってくれるものである。 また「甘美な恋愛」で思い出すのが、大正期を代表する劇作家・岡本綺堂の作品である。 その作品のいくつかは『番町皿屋敷』『修善寺物語』など、いわゆる新歌舞伎として有名である。まだ大学三年生のころだったと思う。綺堂の戯曲集に読み耽ったことがある。「甘美」という点で、綺堂の台詞はプッチーニのオペラの歌詞に勝るとも劣らぬものがある。戯曲集の文字をたどりながら、ほとんどの作品において初演時に二枚目の役を演じた市川壽美蔵の優姿を想像しては、文学と舞台の間隙にたゆたう恍惚感を味わっていた。 だが、事実は小説より奇なり。それから九年ほど経ち、私は市川壽美蔵(のちの三代目市川壽海)に面差しが似るといわれる、壽海の養子に巡り逢う。その人からこの世で最も「甘美な恋愛」を教えられることになろうとは、その時は夢にも思わなかった。 |
| 前・本学幼児教育科田中陽子教授より平成12年1月から1年間、雑誌 『月刊おりがみ』(日本折紙協会)を寄贈していただけることになりました。
4月号では、人気キャラクター“ミッフィー”の作品や、パーティーのときのお菓子入れなどの作り方が紹介されていますのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか? |
| 春風と共に 「ふじざくら No.17」をお届けします。 皆さんが実りある学生生活を過ごせますよう、図書館職員一同お手伝いいたします。 図書館でお待ちしています… |
最終更新日 05/5/2
制作 山梨県立大学(文責:図書館)
Yamanashi Prefectural University