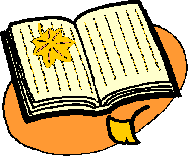-
(山梨大学学生新聞1985.4.10)
-
一冊の本
-
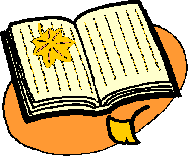
-
伊藤 洋
-
「糸瓜咲いて 痰の詰まりし 佛かな」
-
- ときに1902年9月19日未明,明治の巨人正岡子規は病魔との闘いに明け暮れた35年の短い生涯を閉じました.冒頭の一句は子規の辞世の句です.これが俳句として優れたものかどうか,私には批評する力がありません.ただ,「佛かな」という「仏」は作者自身の亡骸を指しています.むなしく骸となって横たわる自分を,自身が「佛かな」と詠んで客観視しているその態度は,死後の未来との間に自然な連続があって,大きな驚きを禁じえません.
-
- およそ六年に及ぶ子規の闘病の記録は,『松羅玉液』,『墨汁一滴』,『病床六尺』,『仰臥漫録』など一連の新聞連載随筆の中に実にいきいきと描かれています.「最早希望もこの上は小さくなり得ぬほどの極度にまで達したり.この次の時期は希望の零となる時期なり.希望の零となる時期,釈迦はこれを涅槃といひ,耶蘇はこれを救ひとやいふらん」(墨汁一滴)というように,子規の病状はひたすらに悪化の一途を辿りました.そんな中にあって,子規はひたすらに食い,吐き,苦しみながらも,自身の提唱する短歌の改革のために,書き,教え,自身でも多数の作品をものしていくのでした.
-
- 「仰せの如く近来和歌は一向に振るひ不申候.正直に申し候へば万葉集以来実朝以来一向に振るひ不申候.」という書き出しで始まる『歌よみに与ふる書』は旧来の弊風になじんでいた当時の歌人やマニアに驚天動地のショックを与えることになります.「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候.」といって,子規によってやり玉にあげられた古今集は日本人にとっては,それまで和歌の手本と目されていたのです.
-
- この強烈な宣言を見てショックを受けたのは当時の「歌よみ」だけではありません.ただ古典だというので有り難がっていた私の驚きも大変なものでした.その時受けた衝撃は今でもはっきりと覚えています.高校生でいささか文学少年であった私は,その衝撃に遭ってなまなかな文学趣味から決別し,親や高校の先生から勧められた工学を勉強することに決心したくらいなのですから.
-
 前ページへ戻る
前ページへ戻る