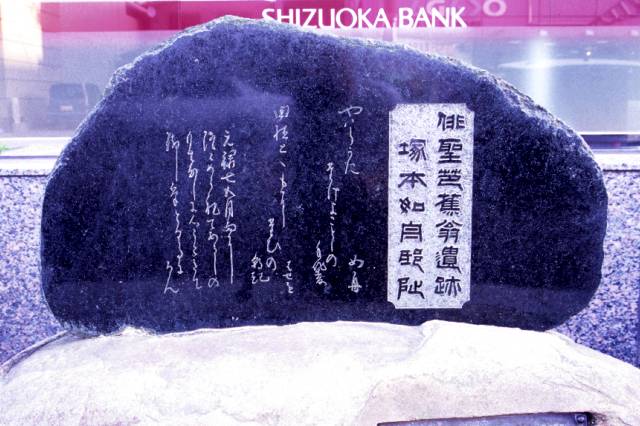-
「芭蕉db
-
島田の時雨
-
(元禄4年10月下旬:48歳)
-
[印] ばせを
-
時雨いと侘しげに降り出ではべるまま、旅の一夜を求めて、炉に焼火して濡れたる袂をあぶり*、湯を汲みて口をうるほすに、あるじ*情あるもてなしに、しばらく客愁の思ひ慰むに似たり*。暮れて燈火*のもとにうちころび、矢立取り出でて物など書き付くるを見て、「一言の印を残しはべれ」*と、しきりに乞ひければ、
-
-
(やどかりて なをなのらする しぐれかな)
-
 句集へ
句集へ  年表へ
年表へ
-

-
宿借りて名を名乗らする時雨かな
-
『奥の細道』の旅以来長期にわたる上方住いから江戸に下る旅の途次、島田の宿で塚本如舟のために書いた一文が『島田の時雨』である。
一句の意味は「宿を借りようとして、大声で名を名乗らせるのは突如降ってきた時雨の所為だ」というのである。
-
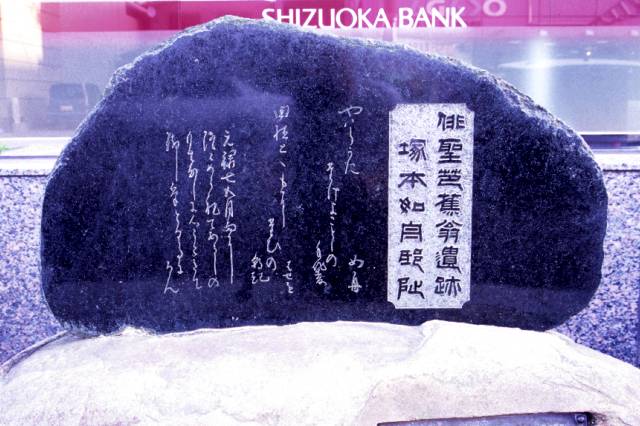
島田市塚本如舟邸跡の句碑(牛久市森田武さん提供)
-

現在の大井川.東海道線車中より
炉に焼火して濡れたる袂をあぶり:<ろにたきびしてぬれたるたもとをあぶり>と読む。
あるじ:この主は塚本孫兵衛。芭蕉門人で大井川の川庄屋。大井川の川越人足数百人を抱える大親分であった。俳号如舟。
燈火:<ともしび>と読む。
客愁の思ひ慰むに似たり:<かくしゅうのおもいなぐさむににたり>と読む。旅の憂いが慰められるような気がした、の意。
「一言の印を残しはべれ」:何か私との交友のしるしに一言書きつけたものを下さい、の意。実際に如舟がねだったかどうかは分からないが、芭蕉は数多く東海道を上下する際、必ず如舟の世話になった。その謝意を込めてこの一文を書いたに相違ない。